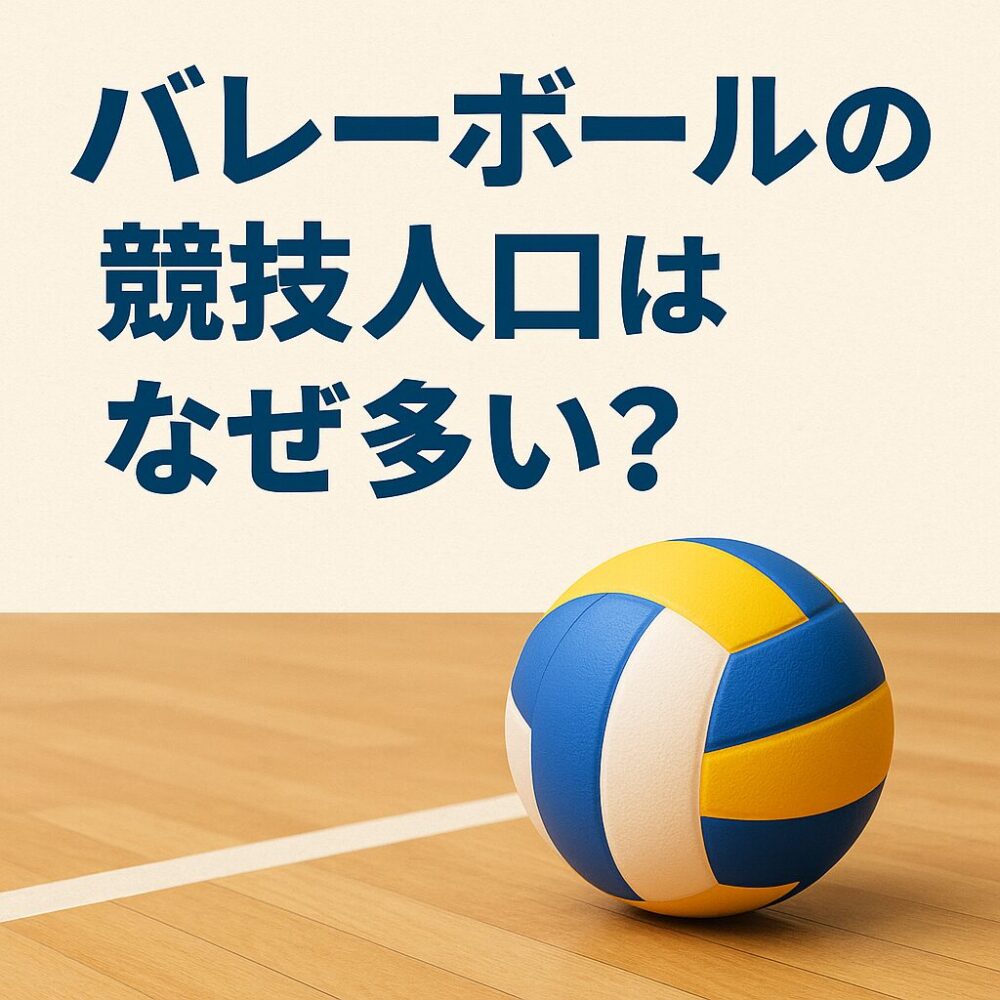バレーボールって、どうしてこんなに競技人口が多いのでしょう?
その答えは超シンプル。
誰でも・どこでも・いつまでも楽しめるスポーツだからです。(筆者もその一人)
2025年時点では、日本国内の登録選手・スタッフが約45万人。参考資料→JVS
しかも、小中高~大学生だけで年間181万人がプレーし、成人層でも217万人が年1回以上バレーボールを楽しんでいるという結果が出ています。
学校の体育、中高の部活、大人のクラブ活動に至るまで、ライフステージを問わず多くの人がバレーボールに関わっています。
この記事では、そんなバレーボールの人気の理由を5つの視点からわかりやすく紹介していきます。
学校の授業や部活動で、誰もが一度は触れるスポーツ
バレーボールは、小学校・中学校・高校と、ほとんどの学校で体育の授業に取り入れられています。
部活動としても男女ともに人気が高く、全国大会も盛り上がっていますよね。
ルールも比較的シンプルなので、先生も教えやすく生徒もすぐに楽しめます。
「はじめてのチームスポーツがバレーだった」という子も多いのでは?
自然と親しみを持ち、クラブや部活につながっていく――。
そうした導線が、競技人口の広がりにつながっています。
男女関係なく楽しめる
バレーボールは男子も女子も同じように大会が開催され、どちらも盛り上がりを見せています。
そして、地域の大会やスポ少では男女混合のチームもたくさんあります。
身体の大きさの大事ですが、技術やチームワークが求められるので性別や体格差に関係なく活躍できるのが魅力です。
「背が低くてもリベロで守りの要に」「力がなくてもセッターで試合を動かす」いろんなタイプの選手が輝けるのも、バレーならではです。
体育館とボールがあればそれでいい
バレーボールは屋内スポーツなので、天気に左右されません。日焼けもしません。
必要な道具も少なく、体育館とネットとボールさえあればすぐにプレーできます。
しかも接触プレーが少ないため、ケガのリスクも比較的少なめ。
小さなお子さんや初心者でも安心して参加できるのが嬉しいポイントです。
学校や地域の施設でも始めやすく、サークルやクラブが自然と増えやすいんですね。
ママさんバレーやシニアバレーのように、年代ごとの楽しみ方ができるのも大きな魅力。
ポジションごとに役割があって、誰もが輝ける
バレーボールには、アタッカー・セッター・リベロなどさまざまなポジションがあります。
「スパイクは苦手だけど、レシーブは得意!」というように、自分に合った役割を見つけやすいのが特長です。
1人で完結するスポーツではなく、誰かがつないで、誰かが決める。
その連携の中に、チームスポーツならではの面白さや達成感があります。
大会や地域活動が盛んで、ずっと続けられる
バレーボールは小学生から社会人、そしてシニア世代まで、どの年代でもプレーの場があります。
市町村の大会やクラブチーム、ママさんバレーやスポーツ少年団など、関わり方も多様です。
一度バレーから離れても、また戻ってきやすい。「昔やってたから久しぶりに再開したいな」という人が参加できる環境が整っているのも特徴です。
だからこそ、競技人口が減らず、むしろ“生涯スポーツ”として定着しているんですね。
まとめ|バレーボールが広がっているのは、「つながりやすさ」があるから
バレーボールの競技人口が多い理由は、
- 学校教育にしっかり根づいている
- 年齢や性別を問わず楽しめる
- 道具も少なく始めやすい
- 役割がはっきりしていて誰でも活躍できる
- 続けやすい地域活動がある
こうしたつながりやすさが、バレーの魅力そのものです。
運動が得意じゃなくても、チームの一員として支え合いながら楽しめる。
その経験が、人生の中で何度もバレーボールと出会うきっかけをつくってくれているのかもしれませんね。